
(図1)
社会的な問題をとりあえげた作品でありながら、語り部を犬のマサにした背景は、重すぎるストーリーを和らげようとしたためなのかもしれません。 しかしながら、続編の短編集「心とろかすような」では、大人を思うように手玉にとるアンファン・テリブル (おそるべき子供) や、老犬マサが犬ならではの目線で人間の動物に対する残虐さを描写するなど、じょじょに犬であることで描写が和らぐというより、犬でしか描写できない人間の内面複雑さのために使われるようになっていきました。
話がそれましたが、犬が語り部である物語から始まり、「龍は眠る」「クロスファイア」や江戸時代を舞台にした「霊験お初」、さらに比較的新しい「楽園」に至るまで、宮部先生は繰り返し超能力・超常能力をテーマに描き続けています。
その真意はともかく、数多くの後の作家−とくにライトノベルやSF・ファンタジー作家志望−に影響を与えたことだけは間違いありません。 「超能力=荒唐無稽、現実離れ、子供向け」という定型を崩して以降、多くの作家が非現実な題材で現実的なテーマを描いていき、またその多くはライトノベルのレーベルやファンタジー小説で発表されています。

(図2)
そのデビュー作「十角館の殺人」 (図2) は一見ファンタジーでもライトノベルでもない、まったく純粋な本格ミステリ (伸ばさないのがミソ) です。 しかしながらその内容・登場人物の思考・ラストなどは、社会派ミステリーに慣れていた読者から当時”現実離れしたファンタジー”のように受け止められます。
宮部先生とは逆に『現実的な題材で非現実なテーマを書く』ことで、綾辻作品はミステリファン以外も虜にし、その読者のなかには「月姫」の奈須きのこ先生もいました。 そして、綾辻先生たちがデビューした講談社ノベルスは、後に奈須きのこ先生の「空の境界」や、現在では講談社BOXとしてライトノベル的な作品を輩出しています。
ひどくまとまりがない内容になってきたので、次回に続くかは分かりません…。
(担当 有冨)



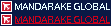
 このページの先頭へ
このページの先頭へ